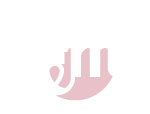「とても多いのに、誤解されやすい腰痛」

「とても多いのに、誤解されやすい腰痛」
腰が痛いと病院で検査をしても、
「骨は問題ありません」「神経も圧迫されていません」
と言われることがあります。
それでも痛みがある——
そのときに多いのが 筋筋膜性腰痛(きんきんまくせいようつう)というものがあるそうです。
これは、筋肉とその周りの膜(筋膜)のこわばりや動きの悪さ、そして動作のクセや神経の疲れが重なって起きる腰痛 です。
単なる“筋肉痛”でもなく、
“姿勢だけの問題”でもなく、
いくつもの要因が積み重なって起きる、複雑な腰痛なのです。
ここでは、その特徴をわかりやすく説明します。
筋筋膜性腰痛は、「筋肉だけ」でも「姿勢だけ」でも説明できない
腰が痛い=筋肉が固い
と思いがちですが、それだけではありません。
● 筋膜がくっついて滑らなくなる
● 身体のどこかに負担がかたよる
● 無意識のクセで身体をうまく使えていない
● 神経が敏感になり“痛みを感じやすい状態”になっている
こうした要素が重なって痛みになります。
特に 筋膜 は、神経がたくさん集まる“体のセンサー”。
筋膜が緊張すると、痛みも動きも大きく影響を受けます。
「動きのクセ」が筋膜の問題を悪化させる
筋肉や筋膜の状態が少し悪くても、動きが上手なら痛くない人もいます。
しかし、次のような動きのクセがあると痛みが出やすくなります。
● 背骨がひとつずつ動かず、かたまりで動く
● 骨盤が反りすぎ、または丸まりすぎ
● 歩くとき、上半身がねじれていない
● 呼吸が浅く、体幹が働きにくい
このようなクセがあると、どこかに負担が集中してしまい、
筋膜の緊張が強まって痛みを出しやすくなります。
つまり、
“動きの悪さ → 筋膜のストレス → 動きがさらに悪くなる”
という悪循環が起こるのです。
痛みには「脳と神経の働き」も関わっている
筋筋膜性腰痛では、身体だけでなく神経にも変化が起きます。
● 痛みの信号を受け取る神経が敏感になる
● 脳が“体の地図(ボディマップ)”をうまく作れなくなる
● 不安やストレスで痛みを強く感じやすくなる
● 自律神経の緊張で血流が悪くなる
痛みは“ただのケガ”ではなく、
脳と神経の反応によって強くも弱くもなる体験 なのです。
筋筋膜性腰痛は、いろいろな方向から整えると改善しやすい
筋筋膜性腰痛は複雑ですが、
逆に言えば「色々な要素を少しずつ整えれば改善が早い」腰痛です。
必要なのは次の5つ。
- 筋肉の固さや弱さを整える
- 筋膜の滑りを良くする
- 体の感覚や神経の反応を整える
- 姿勢や動きのクセを直す
- 呼吸・睡眠・ストレスなど日常のリズムを整える
これらがそろうことで、身体は元の自然な動きを取り戻します。
そして、特に重要なのが「大腰筋(だいようきん)」
腰痛の中でも、私自身がとても重要だと思っている筋肉が 大腰筋 です。
大腰筋は
● 腰の骨(腰椎)
↓
● お腹の奥
↓
● 太もものつけ根
までつながる、とても深い位置にある筋肉です。
姿勢を支え、身体を安定させ、歩く・座る・立つ…
一日中働き続けている“影の立役者”です。
大腰筋が腰痛を起こしやすい理由は次の4つ。
① 姿勢の影響を受けやすい
腰を反りすぎる → 大腰筋が縮みっぱなし
腰が丸くなる → 大腰筋が引き伸ばされ続ける
どちらでも疲れて固まります。
② ストレスで固まりやすい筋肉
大腰筋には“ストレスの神経(交感神経)”が多いため、
心の緊張が、そのまま筋肉の緊張につながります。
③ 呼吸が浅いと大腰筋ががんばりすぎる
胸が固くて呼吸が浅い人は、
大腰筋が呼吸の補助をするために使われすぎてしまいます。
④ 深い場所にあり、血流が悪くなりやすい
大腰筋は体の奥深くにあるため、血流が届きにくく、
疲れがたまりやすい筋肉です。
大腰筋が固くなると起きやすい症状
✔ 腰の前側がつまる
✔ 立つと腰が痛い
✔ 長く座ると腰が重い
✔ 歩くと疲れやすい
✔ 腰が反りやすい
こうした症状がある人は、大腰筋が大きく関わっていることが多いです。
まとめ
筋筋膜性腰痛は
● 筋肉
● 筋膜
● 動きのクセ
● 神経
● 姿勢
● 呼吸
● 生活習慣
これらが複雑に関わって起きる腰痛です。
特に大腰筋は、その中心的な存在です。
だからこそ、
ピラティスで
● 呼吸を整え
● 姿勢を整え
● 動きを滑らかにし
● 深層筋(特に大腰筋)を自然に使えるようにすること
は、腰痛を改善し、再発を防ぐための強い味方になります。
まずは体験!