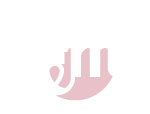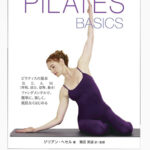「良い動き」とは何か

「良い動き」とは何か──文化的視点と個人差を踏まえたピラティス指導の在り方
ピラティスを教えていると、「正しい動き」「美しい姿勢」といった言葉をよく耳にします。けれども、果たしてそれらの“理想”は本当に万人に共通するものなのでしょうか?
近年の解剖学や運動学の知見、そして教育現場での実践を通して、私は「良い動きとは何か?」という問いに対して、より柔軟で多角的な視点を持つようになりました。
今回は、ピラティス指導者として意識しておきたい「文化的バイアス」と「個別性」の重要性について考えてみたいと思います。

■ 私たちの「理想」はどこから来ているのか?
「良い動き」「正しい姿勢」といった概念は、私たちの経験、教育、そして文化的背景によって形作られています。
ピラティスの創始者であるジョセフ・ピラティスは、北ヨーロッパ出身の白人男性で、彼が著書の中で理想とした背骨の形状は「まっすぐな線」でした。しかし現代では、脊柱には**自然なカーブ(生理的湾曲)**があることが、重力下での効率的かつ安全な動きに必要不可欠であるとされています。
ここで注目したいのが、文化的背景による姿勢や動きの基準の違いです。
たとえば、西洋では椅子に座ることが基本であるのに対し、東洋では床に座る文化が長く続いてきました。トイレにしても、かつての日本では和式が一般的で、しゃがむという動作が日常に溶け込んでいました。また、日本では「立つ」ことにも所作や礼儀が伴い、姿勢そのものが文化的に重んじられてきた歴史があります。
こうした生活様式の違いは、身体の使い方や筋肉の使われ方、そして“自然な姿勢”の基準そのものを変えていきます。
つまり、「良い姿勢」「理想的な動き」とは、必ずしも一つの型に収まるものではなく、文化や環境に応じて多様であるべきなのです。

■ 「良い動き」は見た目ではなく、機能性と適合性
優れたアスリートやダンサーを観察してみると、そこには驚くほど多様な体型・骨格構造・筋肉の付き方があります。それでも彼らが高いパフォーマンスを発揮できるのは、自分の身体に合った動き方を知り、それを最大限に活かしているからです。
ピラティスの指導においても同じことが言えます。
たとえば、ある動きが見た目には「理想的」に見えても、実際にはクライアントにとって不安定であったり、痛みを引き起こすこともあります。逆に、少しフォームが崩れているように見えても、クライアント本人にとっては安定し、安全で快適であることもあるのです。
大切なのは、「この動きがクライアントにとってどう作用しているか?」という視点を持つこと。
つまり、見た目の正しさよりも**機能性(Function)と適合性(Suitability)**を優先することが、プロフェッショナルとしての姿勢だと思います。
■ 観察と対話──動きの質を読み解くために
実際の指導現場では、視覚的な観察とクライアントからのフィードバックの両方が重要な情報源となります。
◯ 観察のポイント:
- アライメント(整列)と対称性の有無
- 動きの滑らかさやタイミング
- 筋連鎖のつながり(統合)
◯ フィードバックから読み取るべきこと:
- 「その動きはどんな感じがするか?」
- 「どこに不安や痛みを感じるか?」
- 「動くことに恐怖や抵抗を感じる瞬間は?」
これらのやりとりから、表面的なフォーム修正ではなく、その人の体に本質的に合った動きの再教育(リパターン)が可能になります。
■ 感覚を研ぎ澄まし、常識を更新する力
このように、一人ひとりの体は異なり、それぞれの背景や経験、文化的要因によって「快適な動き方」も変わってきます。だからこそ指導者自身も、常識にとらわれず、自分の感覚を研ぎ澄ますこと、そして知らなかった視点や感覚を受け入れる柔軟性が求められます。
私たちには、「正解」を押しつけるのではなく、「その人にとっての最適解」を一緒に探し出すサポートをする役割があります。
■ 終わりに──問い続ける姿勢を大切に
「良い動き」とは何か?
その答えは一つではありません。文化的背景、身体的特徴、生活スタイル、過去の経験…それぞれの要素が複雑に絡み合う中で、その人にとってのベストを一緒に探していくことが、真の指導だと思います。
私自身も、指導する立場でありながら、常に問い続け、学び続けたいと思っています。
目の前のクライアントの身体と心に誠実であるために──。
まずは体験!