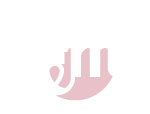【ピラティス器具の歴史と今】

【ピラティス器具の歴史と今】進化する“本物”のカタチとは?
ピラティスのレッスンで欠かせない、リフォーマーやチェア、スプリングなどの器具たち。
私たちが当たり前に使っているこの器具のルーツは、実は今とは大きく異なっていました。
今回は、ピラティス器具がどのように誕生し、どんな経緯を経て現在の形になったのか――
ピラティスメソッドの理解がより深まる「器具の歴史」についてご紹介します。

■ 最初のピラティス器具は“ウェイト式”だった?
ジョセフ・ピラティスが最初に取得した特許では、器具は「Gymnastic Apparatus(体操器具)」と呼ばれ、現在のようなスプリングは使われていませんでした。代わりに、重り(ウェイトスタック)を使用する仕組みだったのです。
驚くことに、今日最も知られているリフォーマーには特許が存在せず、特許があるのはワンダチェアやフットコレクターといった別の器具です。
また、初期のリフォーマーは、ストラップの長さを調整することができませんでした。現在のような可動式ストラップやロープは、後の世代による「進化」の一部なのです。
■ スプリングの誕生とその後の変化
初期の器具では、すべて同じ強度のスプリングが4本使われていました。
しかし、時代とともに改良が進み、現在では異なる強度のスプリングが5本または6本使われるようになっています。
これにより、エクササイズごとにより細かな調整が可能になりました。
ただし、製造過程では±10%ほどのばらつきがあるため、
「同じ強度」とされるスプリングでも、実際の使用感には差が出ることもあるのです。
強度の違いを視覚的に分かりやすくするため、現在のスプリングには色分けされたタブがついているのも、現代ならではの工夫といえるでしょう。

なので、自分のマシンを使い込むこともそのエクササイズを理解し、指導するまでに必要なことだと私は、思います。
■ Balanced Body と現代器具の進化
ピラティス器具の製造で大きな役割を果たしてきたのが、Balanced Body社です。(アメリカでの大手ピラティスマシンメーカー)
彼らはロン・フレッチャーの依頼を受けて器具製作を開始し、80インチリフォーマーなどを開発。
そこに、故ステファン・フリーゼ氏の提案で「第5スプリング」が追加されました。これは、よりコントロール力を必要とするエクササイズのための工夫でした。
また、1980年代には「ライザー(支柱)」が導入され、ストラップの引っかかりを防止。
Kathy Grantの器具には、すでにロープの長さ調整機能がついており、それがモデルとなって現代機器に搭載されていきました。
■ 各社の創意工夫も進化を後押し
Balanced Bodyだけでなく、STOTT PilatesやPeak Pilatesといったメーカーも独自の工夫を重ねています。
- STOTTは金属製器具に移行し、可変式プーリーや第2プーリーを導入。
- Peak Pilatesは、リフォーマーにタワーを追加し、限られたスペースでもキャデラックのように使える設計を実現。
このように、現代の器具はオリジナルのアイデアをベースに、使いやすさや多様性を追求して進化し続けているのです。

■ 同じエクササイズでも「違う」体験になる
同じ名前のエクササイズであっても、使う器具が違えばまったく異なる体験になることがあります。
例えば、「ショートスパイン」というエクササイズ。
80インチの古典的リフォーマー(レザーストラップ、4本の均等スプリング)と、可変スプリング&プーリー付きの現代的リフォーマーでは、動きの精度や身体への感覚がまったく違うのです。
だからこそ、指導者である私たちは、過去と現在の器具両方を知り、実際に体験することで、違いを理解し、適切に指導していく必要があります。
背の高さなどでこの80インチではそのエクササイズの利点を引き出せないこともあるかなと思います。
が、クラシカルピラティスと言われています、ロマーナは、80インチサイズにこだわったとも言われています。
ちなみに、当スタジオのマシンは、STOTT
または、クラシカル86インチサイズとなっています。
■ Kevin A. Bowen氏の視点から
この記事の元になったのは、PMA(Pilates Method Alliance)元会長であり、Core Dynamics Pilatesの代表でもあるKevin A. Bowen氏のリサーチです。
彼は、こう語ります。
「私たちインストラクターは、自分のルーツを知るべきです。同じ名前のエクササイズでも、器具によって感覚は異なります。その違いを体験し、理解し、クライアントに正しく伝えていくことが、私たちの責任です。」
■ おわりに:歴史を知ることで“今”のピラティスがもっと深まる
ピラティス器具は、ジョセフ・ピラティスの思想と、その後の弟子たちの工夫、そして時代ごとのニーズに応じて、少しずつ形を変えてきました。
「本物」にこだわることも大切。
でも、「進化」を知ることも、同じくらい大切です。
それを知ってこそ、私たち指導者は“本質的なピラティス”を伝えることができるのではないでしょうか。
まずは体験!