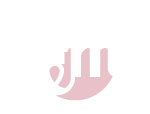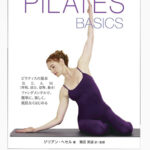側弯症の身体に“まっすぐ”を取り戻す

側弯症の身体に“まっすぐ”を取り戻す
—— 『Analyzing Scoliosis』第11章 “Scoliosis Movement Principles” を読んで
ピラティスを学ぶ中で、側弯症(scoliosis)はいつも私の興味を引きつけてきました。
「背骨のゆがみ」という言葉で片づけられがちですが、実際の側弯症はもっと複雑です。
この第11章では、その「複雑さの中でどう整えていくか」という本質的な問いに、
非常に実践的かつ深い洞察が書かれています。
これをシェアしようと思います。
16次元の歪みを読み解く:プラムラインを再構築する
著者は冒頭で、
「Scoliosis is 16-dimensional(側弯症は16次元的である)」
と語ります。
左右差だけでなく、回旋、前後のずれ、骨盤・肋骨・頭部の不均衡——
身体全体が多方向に影響し合いながら歪んでいる。
だからこそ、単に“曲がりを直す”のではなく、
頭から骨盤までの垂直線(plumb line)を再構築することが重要だと説きます。
この「プラムライン」は、ピラティスの“中心軸”の概念にも重なります。
身体の中に真っすぐな線を感じ取れるようになることが、再教育の第一歩なのです。
正しい方向を知る:前面と側面からの観察
側弯症の身体は、自分の“まっすぐ”を誤認していることが多い。
頭が骨盤の中心からずれていても、本人には真っすぐに感じられるのです。
このため、指導者は鏡を使い、視覚的フィードバックを与えながら再学習させる必要があります。
それが「Correct Front View Alignment」。
さらに横から見た時に必要なのが「Correct Side View Alignment」。
胸椎後弯・腰椎前弯といった自然なサジタルカーブ(前後弯曲)を再び作ることで、
身体の安定性が大きく向上します。
“Reinstating the sagittal curves will help stabilize scoliosis.”
(サジタルカーブを取り戻すことが、安定をもたらす)
この一文に、ピラティスの原理と側弯修正のつながりを感じました。
腰椎L2――「魔法のボタン」
著者は、側弯の多くに共通する特徴として、L2(第2腰椎)が後方に沈むことを指摘します。
この椎骨を空間的に前方へ導くと、腰椎前弯が戻り、全体が整う。
あるクライアントはこの動きを初めて感じた瞬間に、
“It’s my magic button!”(魔法のボタンみたい!)
と表現したそうです。
その感覚をつかむことが、側弯の改善だけでなく、
自分の身体への信頼を取り戻す第一歩になるのかもしれません。
“オーバーコンペンセート”する勇気
「Overcompensate Past Neutral」——つまり、“ニュートラルを少し超えて動く”という考え方。
これはとても印象的でした。
身体に「新しい真っすぐ」を再教育するには、
まずその範囲を少し超えて体を導く必要がある。
そのために使われるのが「Side Bend(側屈)」や「Side Shift(側方移動)」です。
とくにSide Shiftは、肋骨をスライドさせるように凹側へ動かすもので、
「折る」のではなく「滑らせる」動き。
著者はピノキオの人形の糸を例に挙げ、
「凹側を引き上げるイメージを持たせること」
を推奨しています。
Release convex, work concave.
本章を象徴する言葉です。
側弯の身体は、凸側(外側)が常に働きすぎ、凹側(内側)は休眠状態になっています。
まずはこのアンバランスを解きほぐすこと。
凸側を“解放(release)”し、凹側を“働かせる(work)”。
この順序が何よりも大切です。
著者は実際のクライアント「Amber」のケースを紹介し、
**片側だけでの再教育(unilateral work)**を通して
筋肉のスイッチを入れ直していく過程を描いています。
対称性を急ぐのではなく、非対称性を理解し直すこと。
そこに、ピラティス的な誠実さを感じました。
再統合へのステップ:座位・立位・プランク
クライアントが感覚を取り戻してきたら、
座位 → 立位 → プランクへと段階的に統合していきます。
- 座位では鏡を使って呼吸・姿勢を確認
- 立位ではCoreAlign(当スタジオにはないのですが)やBOSUボール上で安定性を高める
- 上級ではプランク姿勢で全身の統合を図る
ここで使われる「BACディスク(Biomechanical Asymmetry Corrector)」は、
非対称性を感覚的に再学習させる優れたツール。
凸側と凹側の双方を等しく働かせるための“架け橋”になります。
そして、コアへ
クライアントが正しいアライメントを維持できるようになったら、
ついにピラティスの中心であるコアワークへ。
“Core work is effective at correcting vertebral rotation and reducing pain.”
(コアワークは椎骨の回旋を矯正し、痛みを減らす効果がある)
すべてのプロセスはここに向かっていると感じます。
整えること、感じること、そして動くこと。
それらが再びひとつに戻る瞬間です。
ウサイン・ボルトに学ぶ「意識の使い方」
章の最後に登場するのは、短距離走者ウサイン・ボルト。
彼の背中の写真を見ると、凹側の筋肉の方が発達しているというのです。
それは、彼が意識的に弱い側を鍛えた結果。
“concave sideを働かせる”というこの章の哲学を体現している例として紹介されています。
「クライアントをボルトのようなアスリートにすることが目的ではない。
それぞれが“自分の最高の状態”を生きられるよう導くことが、私たちの役割である。」
この一文に深く共感しました。
ピラティスは、身体を直すためのものではなく、身体と向き合う方法そのものなのだと。
私自身の想い
私は、側弯を“治す”ことよりも、
その人自身が自分の力でバランスを見つけられるようになることを信じています。
実は私自身も、側弯傾向の動きを持ち、
かつては腰痛に悩まされ、「動くこと」への不安を抱えていました。
だからこそ、今こうして、“動くことが楽しい”と感じられる瞬間を届けられることが、
本当に嬉しく、何よりの喜びです。
その思いを伝えるために、私は多くの本を読み、学び、伝えています。
「運動をすれば健康になる」——
当たり前のように聞こえるけれど、実際には、
動くことが怖くて、楽しめない人たちがたくさんいるのです。
だからこそ、インストラクターは学び続けるべきだと思います。
身体の知識だけでなく、「人が再び動く勇気を取り戻す」ためのサポートとして。
ピラティスを通して、
“まっすぐ”になるのではなく、“自分の真っすぐを見つける”。
この章は、その原点を思い出させてくれる一冊でした。
引用
- “Analyzing Scoliosis: The Pilates Instructor’s Guide to Scoliosis”
Chapter 11: Scoliosis Movement Principles
by Deborah Lessen et al.
まずは体験!