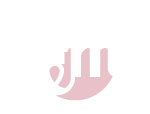座る、その瞬間に込められたピラティスの哲学

座る、その瞬間に込められたピラティスの哲学
ピラティスでは、ただ「座る」だけの動作にも、歴史と意味が息づいています。
アーカイブに残るジョセフ・ピラティスの座り方は、視線をキャリッジ(リフォーマーの台)へと下げ、背骨と重心をコントロールしながら腰を下ろすというもの。
見た目はシンプルですが、実際は繊細なコントロールを要する動きです。
ロマーナの教え
ジョセフの直弟子であるロマーナ・クリザノウスカは、弟子たちに少し異なるアプローチを伝えました。
彼女は「胸を持ち上げたまま座る」ことを指示し、さらに「着地点を見ない」よう挑戦させます。
視線を下げずに動くことで、体幹の安定性と空間感覚を養う狙いがあったのでしょう。

ベス・メンゼンディークの視点
『It’s Up to You』の著者ベス・メンゼンディークは、誤った座り方の例として「足をそろえ、胸を持ち上げたまま腰を下ろし、座骨が突き出る形」を挙げています。
ロマーナは足をそろえるようには教えませんでしたが、それでも胸を高く保ったまま座ると、どうしても座骨が突き出しやすいといいます。

サリのアドバイス
ロマーナの娘、サリはさらに別の方法を提案します。
腰の下部をややすくい込みながら、まるでスカートやズボンの後ろをなで下ろすように、手を太ももの後ろに沿わせて座るというものです。
このイメージは動きを滑らかにしますが、胸を高く保ったまま行うのはやはり難しいという意見もあります。
選ばれた方法
この筆者は最終的に、ジョセフやベスが残したように「視線と頭を下げる」方法を好むようになりました。
胸の高さにこだわるよりも、自然な重心移動と背骨のカーブをコントロールしやすいからです。

私の感じたこと
クラシカル・ピラティスでは、座り方や降り方、エクササイズ間の移動まで丁寧に行います。
かつては、あるインストラクターから「それはただの作法で意味はない」と聞いたこともありました。
しかし、このエピソードを知ると、ジョセフ・ピラティスがすべての動作に合理性と自然さを追求していたことがわかります。
それが時を経て「作法」のような形で残ったのでしょう。
今回語られているのはリフォーマーへの乗り方ですが、おそらくエクササイズ間の移動も同じように、
最適で効率的な方法が考え抜かれていたはずです。
そう思うと、ピラティスというメソッドの完成度と奥深さに、改めて感嘆します。
日常の一瞬の動作さえも、鍛錬の機会に変えてしまう――それこそが、ピラティスの真髄なのです。

参照
- Instagram: @open_access_pilates_archives
- 出典投稿:「Seated mechanics – Joseph Pilates, Romana Kryzanowska, and contemporary interpretations」
- Beth Mendsen Dieck, It’s Up to You
- 著書『Pilates: An Interactive Workbook, If You’re Going to Do It, Do It Right』より一部引用
まずは体験!