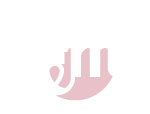チェアが教えてくれる“運動の本質”

チェアが教えてくれる“運動の本質”
ピラティスの各器具には、ジョセフ・ピラティスが意図した明確な「身体教育の目的」があります。
その中でも Wunda Chair(ワンダチェア、ハイチェア、アームチェア、その他コンテンポラリーチェアコンビチェアなど) は、最も“機能的で挑戦的な器具”の一つといえるでしょう。

1. チェアの特性:サポートの少なさが生む「自己統制」
リフォーマーやキャデラックがスプリングのサポートを活かして身体を導くのに対し、チェアは支えが最小限です。
この「不安定さ」こそが、身体の中心(センター)を自ら見つけ出す学びを促します。
多くの動作は、床面からの反力を受け取りながら行われます。チェアではその接地面がペダル一枚であり、重心の移動・骨盤の傾き・胸郭の回旋など、わずかなズレが全身に影響を与えます。
つまり、チェアは「自己組織化」のトレーニング。自らの神経系と筋骨格系が、バランスを探しながら最適解を見つけていくのです。

2. 動きの起点を学ぶ:脚の重さを“使う”
ペダルを押す動作は、脚の力だけで行うものではありません。
「脚を使う」ではなく「脚の重さを利用する」 という視点が重要です。
股関節から足底までのラインを整えながら、脚の重さを骨盤に伝え、そこから脊柱へと動きを波及させる——。
この連鎖が、ジョセフが言う“whole-body movement”そのものです。
特に「Footwork」や「Pull Up」などのエクササイズでは、脚の重さをどのように床(ペダル)へと伝え、どのように背骨を反応させるかが、動作の質を決めます。
足底から頭頂までの連続性を“見抜く目” が、指導者には求められます。

3. チェアが導く“選択の力”
チェアの魅力は、同じ動きをしても“どの筋をどの順で使うか”によって、まったく異なる結果を生むことです。
正しい姿勢を取ることよりも、「どのようにそこへ到達するか」というプロセスに価値がある。
その観察と修正を通して、クライアント自身が自分の動きを“選択”できるように導くことが、チェア指導の醍醐味です。

4. チェアで培われる“見る力と導く力”
スタジオピラティスリムーブの研修でも、チェアは「観察眼を育てる教材」として扱っています。
なぜなら、動きの小さな変化が全身の連鎖に表れるため、“体の声を読む” 練習になるからです。
同時に、インストラクター自身も、動きを言葉ではなく**「体感で導く」**力を磨くことができます。
終わりに
チェアは決して派手な器具ではありません。
けれど、その静けさの中に、身体の真理が隠れています。
それは、“コントロールとは、支配ではなく調和である”ということ。
指導者として、チェアを通して「教える」から「気づきを促す」へ。
そんなレッスンを、これからも大切にしていきたいと思います。
まずは体験!