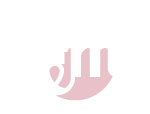脊柱側弯症

scoliosis
脊柱側弯症と姿勢の歪み ― ピラティス指導者としてできること
「脊柱側弯症」という言葉には、二つの側面があります。ひとつは医師が診断する「病気」としての側弯症。もうひとつは、私たち運動指導者が現場で扱う「姿勢の歪み」としての側弯傾向です。これらは同じように見えても、意味するところが少し異なります。
医学的にみた脊柱側弯症
医学的には、脊柱側弯症とは正面から見て脊椎が左右に曲がり、Cobb角が10度以上のものを指します。側弯症には二つのタイプがあり、ひとつは椎体のねじれや変形を伴わない「非構築性側弯症」で、原因を取り除けば改善する場合があります。もうひとつは椎体の回旋や楔状化を伴う「構築性側弯症」で、その中でも最も多いのが原因不明の「特発性側弯症」です。
特発性側弯症は成長期に進行しやすく、20~30度以上では装具、40度以上では手術が検討されます。放置すると80度を超えて呼吸機能や生活の質に影響を及ぼすこともあるため、医療での管理が必要です。

参照
運動指導の現場で出会う歪み
一方で、私たちが日常的に目にするのは、必ずしも診断基準に達しない「歪み」や「側弯傾向」です。かばんを同じ肩に掛け続ける、片足に重心をかけて立つ、デスクワークで片側に傾くなどの生活習慣によって、背骨や骨盤に左右差が生まれます。これは「非構築的な歪み」であり、運動によって改善が期待できる領域です。
ただし、ここで大切なのは、歪みは静止時だけに現れるものではなく、
動きの中で強調されることがあるという点です。
歩行やロールダウン、サイドストレッチといった動作の最中に、背骨の曲がりやねじれがより顕著になることがあります。これは放置すれば体にさらなる負担を与えるため、動きを観察する視点が不可欠です。
ピラティスで得られる「動的な安定性」
ピラティスの大きな特徴は、筋力強化やストレッチにとどまらず、動きの中で安定性を獲得できることです。
背骨や胸郭、骨盤を多方向に動かしながらもコントロールすることで、
- 硬く縮んだ筋を緩め、反対に弱い筋を働かせる
- 呼吸を通して胸郭の左右差を整える
- 「センターを意識する」感覚的に再学習する
といった効果を引き出すことができます。これにより、クライアントは「動いても崩れない体」を手に入れ、日常生活での快適さやパフォーマンスの向上につながります。
指導者としての役割
私たちは医師ではありません。診断や治療は医療の領域であり、そこに踏み込むことはできないと、私は、考えています。
しかし、だからこそ「動き」を専門とする私たちにできることがあります。
それは、クライアントの歪みや左右差を丁寧に観察し、動きの中でどのように現れるかを見極めること。
そして、エクササイズを通して修正を促し、動的な安定性を養うことです。
また、必要に応じて医師の診察を勧める判断力も欠かせません。
さらに、クライアントに「運動でできることがある」と伝えることは、大きな安心感をもたらします。自分の体に不安を抱える人にとって、その一言が前向きに体と向き合う力となるのです。

まとめ
脊柱側弯症は、医学的にはCobb角10度以上を診断基準とし、進行度に応じて治療が行われる病気です。一方で、私たちが運動指導の場で扱う多くは、筋肉のアンバランスや生活習慣による「歪み」です。
ピラティスは、単に姿勢を整えるだけではなく、動きの中でも崩れない安定性を育むことができます。
医療の領域を尊重しつつ、運動指導者として「動的な安定性を引き出すサポート」を行うことが、私たちに与えられた大切な役割だと感じています。

まずは体験!