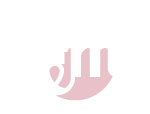クラシカルピラティスって何?

クラシカルピラティスって何?
最近「クラシカルピラティス」という言葉をよく耳にします。けれども、その意味が少し曖昧に広がっているように感じる方も多いのではないでしょうか。今日は私自身の見解を整理しながら、このテーマについて考えてみたいと思います。
何度もこのテーマについては考えていますが、なかなか今は、私の考えとは違うような気がしています。そして、それら違いを認めることではなく、何か、これと決めたがっているふうにも見えます。
クラシカル=ロマーナの系譜
私が思うクラシカルピラティスとは「ロマーナ・ピラティス」に代表される流れです。
ロマーナ・クリザノウスカは、ジョセフ・ピラティス本人から直接学び、その教えを守り続けた重要な存在。初めて、ピラティス指導者を育てるコースを作り体系立てたのが、ロマーナです。ピラティスは、養成コースのようなものがしていませんでした。
当時、マスターインストラクターと認められるにはおよそ600時間以上もの徹底したトレーニングが必要だったといわれます。その厳格さと継承の体系こそが「クラシカル」と呼ぶにふさわしい基盤なのだと思います。つまり、ただ名前を使うのではなく、しっかりとした根拠と考え方を理解してこそクラシカルを伝えられると考えていたのです。
「クラシカル」という言葉の一人歩き
一方で、最近は「クラシカル」という言葉が独り歩きしているように感じます。
それぞれの指導者がクラシカルの響きをブランドとして使い、本来の背景から離れてしまうことも少なくありません。
もちろん流派やスタイルの違いがあるのは自然です。
ただ、クラシカルと名乗る以上、その歴史や練習体系を理解し、責任を持って伝える必要があると私は、考えています。

初心者には向かない?
正直に言うと、クラシカルピラティスは初心者にはややハードルが高いと感じます。
ピラティスを「これから始めてみたい!」という方には、クラシカル以外のやり方の方が入りやすいかもしれません。クラシカルはクラシカル専用のマシンを用い、しかもその負荷に対応できるだけの体の強さが求められます。
ただし、インストラクターを志す方にとっては、学びを深めていく中でクラシカルに触れることは避けて通れないのかもしれません。なぜならクラシカルの動きはピラティスの源流の元々の部分であり、そのエクササイズは誰がやっても同じ形であり、だからこそ「どのマシンを使ってその動きを高めるのか」というマシン(器具)に対する判断力が必要になるからです。動きの質を高めていく感覚も、ピラティスのコンセプトを理解していることが前提になります。
伝統と現代的な導入のバランス
クラシカルの動きは伝統的で、源流であるがゆえに研ぎ澄まされた厳しさがあります。
一方で、初心者にはもう少し穏やかに、ゆっくりと体を慣らしていける流れが望ましいと考えます。
この点で私は、ピラティスは「寿司屋さん」に似ていると思っています。
- 回転寿司は手軽で、誰でも楽しめます。海外ではアボカドや火を通した具材など、その土地に合わせた工夫もされています。
- 一方、本格的な寿司職人は、魚の扱いから長年修行を積み、繊細な技術を提供します。そのぶん値段は高いですが、そこには圧倒的な価値があると考えられています。
クラシカルピラティスも同じで、まずは気軽に「ピラティスを体験する」入り口があっていい。けれども、深く学び、職人の世界に足を踏み入れるならば、クラシカルの厳密さと価値を避けて通ることはできません。

まとめ
クラシカルピラティスとは、ロマーナをはじめとする直系の教えを守り、尊重し、長い時間をかけて磨き上げられた体系そのものです。
初心者にとってはやや難しい一面もありますが、インストラクターにとっては必ず学びたいと思う源流。それが理解できるとピラティスは理解できると考えてもいいからです。
寿司に「回転寿司」と「寿司職人」が共存するように、ピラティスにも入り口としての柔らかい形と、本格的な厳格なクラシカルの世界が共存しています。
そして最後に――
どの形を選ぶのかはお客様自身の選択であり、その価値をどう感じるかも人それぞれ。
では、あなたはどの寿司屋さんを選びますか?
まずは体験!