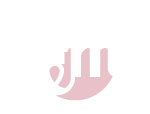クラシカルピラティスは「型」ではなく「本質」だった——私がその学びを深める理由

クラシカルピラティスは「型」ではなく「本質」だった——私がその学びを深める理由
■ クラシカルへの抵抗感——その背景
私はこれまで、クラシカルとコンテンポラリーの両方を学んできました。けれど正直に言うと、クラシカルピラティスには、当初強い抵抗感がありました。
理由は明確です。
- クラシカルはピラティス氏が教えたそのまま、、、が、創始者ジョセフ・ピラティス本人に学べるわけではない(なくなっているから)
- 「ルールが厳しい」「自由がない」という先入観
- 現代のお客様には合わないかもしれないという実感
- ”流派”の押しつけになってしまう懸念
「もっと今のクライアントに合った柔軟なアプローチがあるのでは?」そんなふうに感じていたのです。

■「Hidekoはクラシカルが合うと思うよ」と言われて
そんな私に、ある方がこう言いました。
「Hidekoさんは、クラシカルがすごく似合うと思う。」
その一言が、心の中で静かに、でも大きく響いたのです。
なぜなら、コンテンポラリーで自由なバリエーションを広げていく過程で、ふと、自分の指導の軸やエクササイズの根拠に疑問を感じることがあったからです。
現場では「目的に応じてバリエーションを選択する」ことは重要です。しかしその判断の質を高めるためには、やはりオリジナルの“型”を知っていることが必要だと痛感しました。

■ 実際にクラシカルを深めてみて
クラシカルピラティスのエクササイズは、やはり強度が高く、マシンの負荷も独特です。動きの流れにコントロールも必要で、途切れがなく連続性と精度が要求されるため、かなりの体力と集中力が求められます。
しかし、それこそがジョセフ・ピラティス氏の思想なのだと思います。
- Return to Life(身体の再教育)
- 全身の統合性を取り戻す動きの連鎖
- 器具のデザインに込められた機能的負荷
クラシカルのシステムを身体で“通過”することで、はじめて見えてくる身体の統合感、流れるような中枢神経系の活性、そして骨と深層筋を使うという本質。
たとえ一部のクライアントにそのまま提供しなくても、それを学ぶことで、指導者としての解像度は間違いなく上がると感じます。それは、クラシカルには、本質がしっかりあるからです。

■ 「クラシカル」は、歴史ではなく“再現可能な哲学”
私が特に深く感動したのは、クラシカルピラティスが単なる“歴史的再現”ではなく、エクササイズを通じて、創始者の思考と哲学が今なお体現されているという点です。
ジョーの言葉、呼吸のリズム、負荷の方向性、身体のエネルギーの通り道——それらが、エクササイズの構成・順序・マシンの構造にすべて織り込まれています。
これはもはや「クラシカル」という名称にとらわれるものではなく、ピラティスの根本的な知の集積なのだと、今は感じています。

■ クラシカルを「知る」ことは、指導の自由度を高める
もちろん、クラシカルだけが正解とは思いません。
指導者は、対象者に合わせて適切なエクササイズを選び、提供すべきです。
けれども、もしあなたが指導者としての「軸」を持ちたいのであれば、ぜひ一度、クラシカルピラティスに本気で向き合ってみてほしいのです。
クラシカルは決して「縛り」ではありません。むしろ、自由のための土台であり、「応用のための原理原則」なのだと、今では確信しています。
私の師、Risaは、クラシカルは、本物のピラティスであり、器具も優れていると言います。
そして、それには訓練が必要であり、それが、ピラティスの本質に触れるものであると思っています。
私は、今では、自分でもクラシカルはハードなものであるけど、体の中に何か感じるものがあります。ピラティス氏の情熱が伝わってきた時、何かが体の中で変化となり、私の体を安定させ、成長させてくれるものだと信じています。
まずは体験!