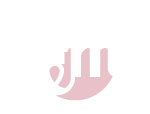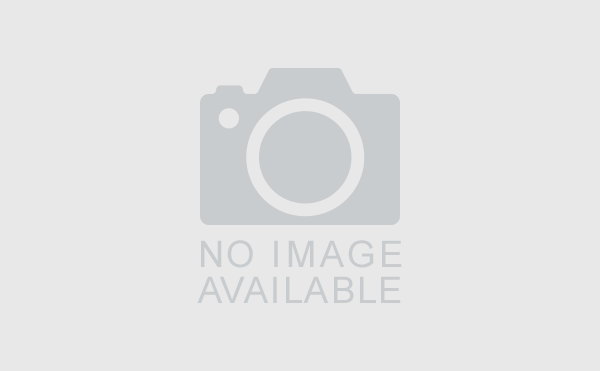運動の「やりすぎ」がもたらすリスク──ジョセフ・ピラティスの原則に学ぶ、効率的な身体の使い方

ピラティスは、単なるエクササイズの枠を超えた「身体の教育法」です。創始者ジョセフ・ピラティスは、「コントロロジー(Contrology)」と名付けたこの体系を通じて、身体と心の機能を意識的に再教育し、調和のとれた健康状態を維持・回復する方法を提案しました。
彼の著書『Return to Life Through Contrology』の中で繰り返し強調されているのが、「エクササイズの回数を多くしないことや強度の限度を見極めることの重要性」です。

◆ 運動は多ければ多いほど良いわけではない
ピラティスは、筋肉を疲労させるためのトレーニングではありません。むしろ、ジョセフは「指示された回数以上にエクササイズを繰り返すことは、害になる」とまで明言しています。
その理由は明確です。必要以上に運動を繰り返すことで、筋疲労を引き起こし、本来の目的である身体機能の改善や調整とは逆方向へ進んでしまうリスクがあるからです。これは、「質より量」ではなく、「量より質」を重視するピラティスの本質を示しています。
◆ 身体を守るのは「備えられた機能」である
ジョセフ・ピラティスは、身体の健康状態を「消防署」に例えています。
体内には本来、免疫や自然治癒力などの“防衛機能”が備わっていますが、身体が整っていない状態では、それらが適切に機能できません。
例えば、姿勢が崩れ、呼吸が浅く、血流が滞っている状態では、外的ストレスやウイルスへの抵抗力も弱まり、病気や不調に対応しきれなくなります。
ピラティスの実践は、これらの「防衛システム」を整えるための具体的なアプローチであり、単なる筋力強化ではなく、全身のバランスと機能性を高めることに主眼を置いています。
◆ トレーニングは「目の前の身体」に合わせて設計すべき
ピラティスでは、一人ひとりの身体の状態に応じて、エクササイズの内容・順番・回数を柔軟に調整することが求められます。
画一的なメニューや一律の負荷設定では、真の意味での身体改善は難しく、時には逆効果となることもあります。特に、弱化した筋群や協調性に欠ける部分に過剰な抵抗を加えることは、動作の質を損ない、誤った代償動作を引き起こすリスクがあります。
そのため、トレーニング設計は「現状に応じた目的」を明確にし、必要な動きと強度を的確に選択することが重要です。すでに正確な動きが定着している場合にのみ、段階的に負荷を上げるべきであり、導入段階では最小限の刺激から始めるべきです。

◆ 回数ではなく「気づき」が目的
ピラティスの真髄は、エクササイズの回数をこなすことではなく、「身体の気づき」を高めることにあります。
数回繰り返すだけでも、自身の身体の癖やアンバランス、可動域の限界が明らかになることがあります。これは、神経系と筋系の協調を通じた再教育のプロセスであり、繰り返すこと自体が目的ではありません。
ピラティスにおいては、「10回きれいに動くこと」は、「100回雑に動くこと」よりもはるかに意味があります。つまり、精度と集中力を伴った動作が、最も効果的な身体づくりにつながるのです。

◆ 身体の限界は、回数ではなく質で見極める
ピラティスにおいては、「すでに最初の数回で限界に達しているかもしれない」という視点を持つことが、質の高いトレーニングへと導きます。
無理に「もっと動こう」「もっと負荷をかけよう」とするのではなく、「今、この動きにどれだけ意識を向けられているか」を問い直すことが、身体を進化させる鍵です。
運動は「多ければいい」ではなく、「的確であること」が重要。ピラティスの原則は、それを理論的かつ実践的に私たちに教えてくれます。
これこそが、年齢や体力に関係なく、多くの人がピラティスで成果を上げている理由でもあります。

このような考え方をベースに、私たちのスタジオでは、単なる動きの模倣ではなく、「理解し、感じ、整える」ためのピラティス指導を提供しています。
もし、自分の身体をより深く知り、効率よく整えていきたいと感じている方は、ぜひ一度体験にお越しください。
まずは体験!